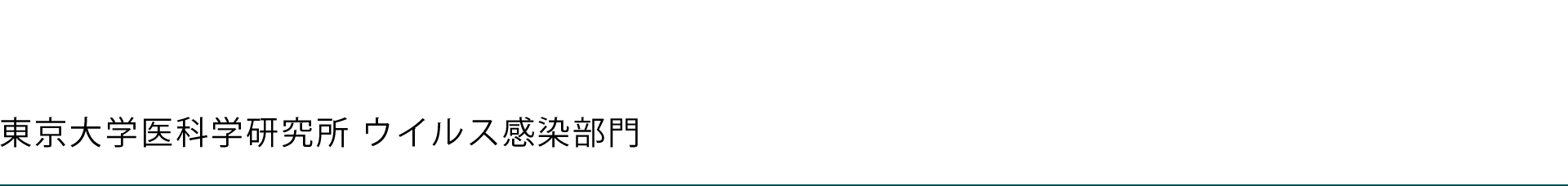研究活動
学会報告
- Options IX for the control of influenza (2016/8/24-28)
- The fifth ESWI conference @ Rigta, Latvia (2014/9/14-17)
- 獣医学会 (2014/9/9-12)
- IUMS 2014 (2014/7/27-8/1)
- Keystone symposia (2014/1/19-25)
IUMS 2014 (2014/7/27-8/1)
7月27日から8月1日まで、モントリオールで開催されたIUMS2014に参加した。日本の学会とはまた違った雰囲気を味わえ、非常に充実した時間を過ごすことができた。
学会開催期間中、午前中は毎日テーマ毎に各分野の研究者による講演が行われた。
Christina Risco氏は、CLEM, TEM, トモグラフィー, タグ融合タンパク質の標識など、数種類の電子顕微鏡手法を組み合わせてウイルス感染細胞の解析を行っていた。メタロチオネイン融合NPを作製する際にRisco氏の論文を参考にしていたので、氏の講演は楽しみにしていた講演の一つだった。低倍率でクライオ電顕を用いてトモグラフィーを行い、感染細胞内の細胞小器官の構造を再構築した図が美しく、印象に残った。クライオ電顕を用いた感染細胞のトモグラフィーは、Ralf Bartenschlager氏 (HCV)、Clodagh O’Shea氏 (アデノウイルス)らによっても行われていた。講演で見た感染細胞内小器官の再構築像はどれも細胞の高さがあり、感染細胞内における細胞小器官の三次元的な位置がより具体的に把握できた。以前、ラッサウイルス感染細胞内における小胞状構造物の再構築を試みたが、TEMでのトモグラフィーのため切片の厚さに限界があり、講演で見たような厚みでトモグラフィーを行うことが出来なかった。さらに、樹脂に包埋した切片を用いたトモグラフィーでは、電子線により樹脂が伸縮してしまうため、小胞が楕円形になる。感染細胞内など、観察する対象に厚みがあり、ある程度の大きさがある場合は、クライオ電顕を用いた方が良いと思った。
O’Shea氏は、miniSOGというタンパク質を用いてCLEMを行っていた。miniSOGは488nmの波長で励起され蛍光顕微鏡下で観察可能になると同時に、電子のexcitationが起き電子密度が高まることで、電子顕微鏡下でも局在が観察できるようになる。O’Shea氏の研究では、miniSOG融合タンパク質の局在を蛍光顕微鏡下で確認したのち、クライオ電子顕微鏡でトモグラフィーによるminiSOG融合タンパク質の局在の再構築が行われていた。融合タンパク質による標識は、目的タンパク質との距離なく特異的に標識されるため、非常に有用だと思った。しかし、TEMでminiSOGを確認しようとすると、染色液内の重金属とminiSOGの標識が被ってしまうため、クライオ電顕など重金属による染色が必要ない観察方法でないと使用できないと思われる。抗体や金粒子の添加が必要ないタンパク質の標識方法は非常に有用なので、機会があれば使用してみたいと考えている。
Bartenschlager氏は、電子顕微鏡を用いた手法のみでなく、分子生物学的手法も組み合わせてHCVの感染細胞内におけるゲノム複製の場を解明していた。以前私も免疫電顕により、ラッサウイルス感染細胞におけるゲノム複製の場を確認しようとしていたので、氏の、HAタグで小胞を精製し、詳細に解析する手法は参考になった。また、Risco氏もTogavirusのポリメラーゼにメタロチオネインタグを付加し、抗dsRNA抗体とともに免疫電顕し、togavirusのゲノム複製の場所を突き止めていた。こういった手法を参考にして、アレナウイルスでもゲノム複製の場所を突き止めることができないか考えたい。
John Johnson氏による講演では、検出機器の性能が向上したことにより、ここ3年で、電子顕微鏡、とくにクライオ電顕の性能が飛躍的に上がったことが言及されていた。本学会では、クライオ電顕を用いた研究の多さに驚いたこともあり、常に先端の技術を意識することの重要性を感じた。
学会では、講演・口頭発表・ポスターを通し、抗体に関する研究が多かった。講演では、Arturo Casdevall氏が、抗体は細胞と微生物の橋渡しをするのみでなく、直接微生物に働きかけることができる、と、抗体の多機能性を強調していたのが印象的だった。
Lynn Enquist氏による講演では、alphaherpes virusのゲノムに3種類の蛍光タンパク質の遺伝子を組み込み、それぞれ異なる色の蛍光を発色する3種類のウイルスを使用した実験が紹介されていた。実験では、ヘルペスウイルスの再活性を引き起こすウイルス粒子の数を調べるため、異なる色の蛍光タンパク質をコードしたウイルス粒子3種類を混合し、それをLow MOIで細胞に感染させ、感染細胞の蛍光色をライブイメージングにより観察していた。動画が美しく、インパクトがあったので、自分の研究にも機会があれば取り入れたいと思った。
腸内細菌のLPSがウイルス粒子をaggregateさせ、ウイルスの感染能を上げることを突き止めたJulie Pfeiffer氏、ウイルスの持続感染時における免疫反応を昆虫で解明したCarla Saleh氏、胎盤で高度に発現しているC19MCというmiRNA群(その中でも特定の4種類)がautophagyを引き起こすことで、幅広い種類のウイルスの感染を阻止していることを明らかにしたCarolyn Coyne氏らは、その研究内容はもちろん、プレゼンテーションが単純明快でわかりやすく、素晴らしかった。
IUMSの講演では日本のウイルス学会と異なり、女性の発表者が多いことに驚いた。また、たくさんのスライドやポスターを見たことで、今後の自分の発表の改善点が見つかった。英語は抑揚や強調がしやすいので日本語での発表とは異なる部分もあるが、プレゼンの話し方の部分でも、今後の参考になる発表が多かった。
自分の発表では、大変緊張したが、無事発表できた。
講演や発表から学んだ研究方法のみでなく、プレゼンテーションの技術に関しても学ぶことが多く、非常に有意義な時間を過ごした一週間だった。
IUMSに参加したことで、数多くの素晴らしい研究や、年齢が近い学生の発表を聞いたことで、非常に良い刺激を受けることができた。また、参考にしていた論文の著者の発表を直に聞くことができ、感動した。クライオ電顕を用いたトモグラフィーの再構築像が自分のトモグラフィー像と比べ物にならないほど綺麗だったので、TEMとクライオ電顕による違いも大きいとは思うが、美しい電顕像を撮影することに関してのモチベーションが高まった。Bridging sessionでのバクテリアやfungiの発表も、普段なかなか聞く機会が無いため興味深かった。
IUMSで得たことを今後の研究や発表に最大限取り入れ、機会があれば再度参加したいと思った。
D1中津 寿実保
カナダ・モントリオールで開催されたIUMS2014はDr. Julian Daviesのオープニングレクチャーから始まった。Dr. Julianは微生物とは我々の生命と切っても切り離せない関係にあり、免疫応答や代謝といった様々な部分で繋がっている故に、微生物の研究をそういったマクロな視点で進めていくことが重要だと説明しておられた。近年、この学会でのいくつか演題があったが、細菌に刺激された免疫応答がウイルス感染に影響を与えるという報告が多々なされており、このような視点を常に意識することは今後のウイルス研究で重要かもしれない。
2日目以降、様々な分野の発表が行われた。各日程で興味深かったり、勉強になったりしたことを以下に示す。
<2日目>
Dr.Cristina Riscoは免疫電顕を用いた細胞内におけるウイルス局在について発表をしていたが、MT(メタロタイシン)を付加させた蛋白質を用いた電顕法は、抗体を用いた方法に比べ感度がよく便利だと改めて認識させられた。実際に実験に使う場合はMTと蛋白質の相性も検討すべきだと思うが、1つのツールとして非常に興味深かった。興味深い発表と言えば、同じPlenary sessionのDr. Lynn Enquistの研究も大変面白いと感じた。ヘルペスウイルスが感染する際に必要な粒子数や感染が広がるために必要な感染細胞数について、レポーター遺伝子を組み込んだウイルスを用いてイメージングを行っていた。発表されたデータの中には解釈が難しい部分も多少あったが、感染様式を調べるうえで様々なレポーターをもつウイルス数種類を用いて解析する方法はインフルエンザウイルスでも十分応用可能だと考えられる。
その日のworkshopは自分も演題発表を行ったVaccine sessionの発表を主に聞いた(後半の一部はインフルエンザのsessionを拝聴した)。
自身のVaccineの発表は幸い多くの人が参加してくださり、かつ質疑等も比較的にしっかりと答えられたと思う。その他の発表は、僕のPB2KOウイルスもそうであるが、ベクターを用いたワクチンの発表が多かった。ベクター型ワクチンは以前から注目されており、ウイルス感染に対する治療のみならず癌などをターゲットにしたワクチンも近年報告されているので、1つの熱い分野なのかもしれない。Vaccine sessionの中で1つ興味深かったのはインフルエンザのHAにa-GALを付加させたワクチンだ。メカニズムについては話していなかった(と思う)がHAにa-GALを付加することによりワクチンの効果が高まるという内容であった。a-GAL付加が立体障壁を生み出すことが重要なのか、付加するものがa-GALであることが重要であるのかという疑問は残ったが、アプローチは興味深かった。またこの日のポスターセッションで、HA-stemの一部の領域を搭載した二価ワクチンの開発(Dr. Dermodyのラボ)についての発表があったが、彼女の仕事ではHA-stem領域を搭載してもHAに対する抗体はほとんど誘導されないということであった。HA-stemとしての構造を保っていない故なのか、そもそも用いた領域が少なすぎたのかは不明だが、ベクターに抗原領域を搭載すればよいという単純な話ではないようだった。驚いたことに、今1つの流行だと感じていたユニバーサルワクチンについての研究発表はほとんどなかった。もうすこし、ユニバーサルワクチンについての議論をしたかったのでその点は残念であった。
<3日目>
その日のPlenary sessionはDr. Lisa F.P. Ngのαウイルスの病原性発揮やそれに対するワクチン等の講演から始まった。ウイルスが感染したのちに急性期そして、慢性期へと移行する際のサイトカインの誘導や抗体誘導についての知見から、どのような抗原がワクチン候補となるのか説明していた。αウイルスのワクチンとしてE3EP3タンパク質を含むVLPワクチンが候補の1つで、その際CD4が重要だということだった。なぜVLPワクチンを用いたのかという疑問は残ったが、VLPに搭載させることでタンパク質の3次構造を保つうえではいい方法なのかなとも感じた。河岡先生の講演も行われたが、Dr. Chengjunの仕事量に圧倒されてしまったが、よい刺激になった。バイオセーフティーの観点から行っている実験の有用性について説明されていたが、否定的な意見を述べる研究者が多いことに驚くと共に、「研究⇔バイオセーフティー」の問題はこれからもっと避けられなくなるだろうという印象を受けた。午後のworkshopでは中津さんと山地さんの発表もあったInfluenza Virusのセッションに参加した。二人とも堂々としていて素晴らしかった。興味深かったのは、インフルエンザウイルスのCap-snatchingの特異性について次世代シークエンスを用いて解析をしていた発表である。Cap-Snatchingはすでに存在するmRNAの中で、量そのものが多いmRNAをランダムにハイジャックしていると思っていたが、Cap-snatchingはランダムではなくある程度特異的配列で制御されているということだった。この現象が他の株でも同じなのか(この発表ではH3N2ウイルス)気になった。質疑応答でChairmanがこの発表を全否定していて、「国際学会ならでは」の議論に少し興奮を覚えた(少なくとも日本の学会では今まで発表者の発表を全否定する人を見たことはなかったので)。
<4日目>
この日、僕が参加したWorkshopはInnate Immunityのsessionである。自然免疫に関する知見を学ぶために参加した。まずDr. Ganes Senがウイルス感染における自然免疫の知見についてわかりやすく説明していた。特に最近RNAセンサーとして注目されているIFITについての講演していた。IFITファミリーの中でもIFIT2がVSV感染抑制には重要であることが示されていたので、他のRNAウイルスでも同様の作用機序で感染抑制がおこるのか調べてみたい(まずは論文等で)。同様にIFITのRNA認識についてphD 学生のMr. Abbasが発表していたが(あまりにすごい髭で初日から注目していた方だった)、IFITのポケット部分のポジティブチャージ領域がRNAとの結合に重要であることを構造から推測し、さらにIFITは5’PPP-ssRNA と結合できること示していた。面白いことに5’PPP-に続く配列はdsRNAを認識できないが、やNNNdsRNAであれば結合可能ということで、5’側のPPP+数塩基が重要であるということだった。dsRNAであっても5’側の数塩基がssRNAであればセンサーに認識される可能性があるというのは、非常に興味深く他のセンサー蛋白質でも似たような現象がある可能性があると思う。Dr. Michaela Gackの発表は最近Cell Host and Microbeにでたデータであったが、麻疹ウイルスのV蛋白質が彼女のグループが発見したリン酸化酵素PP1をハイジャックすることによって、MDA5から始まる免疫応答を回避しているという話だった。今回のこのsessionを聞いて、RIG-IやMDA5による認識機構もまだ不明な点が多く改めて、学問として興味深いと感じた。
<5日目>
この日の朝のsessionでは、Dr. Julieは腸内細菌がウイルス感染に及ぼす影響について発表をしており、ウイルス同士のAgglutinationが感染においてメリットとして働くと言っていたのが印象的だった。一般的にAgglutinationは感染性を低下させる現象なのでウイルスに何のメリットもないと思っていたが、感染性さえ低下していなければ、1回の感染で凝集している数種類のウイルスを同時に感染させることができ、ウイルス側にメリットがあるということだった。Agglutinationに対して否定的な見方しかしていなかったがインフルエンザウイルスにおいても何かしらメリットのようなものが実験的に示すことができるのかもしれない。午後のworkshopではDr. Julieは、「CVB3が腸内環境にさらされることによって変異を獲得する」という内容についてウイルス学的なアプローチで説明をしていた。宿主との関連性も明らかになるとより生体内で何が起きているのかわかるのではないだろうか。
Novel sessionでは、ウイルスはユビキチン・蛋白質分解経路を逃れるように進化してきたと話していたDr. Aalon Ciechanover、ワクチンの効果が強い急性感染症と逆にワクチンの効果が低い(もしくはワクチンが存在しない)慢性感染症について、免疫システムの比較を行いながら話をされていたDr. Rolf Zinkernagelによる講演が行われた。特にDr. Rolfは、スライドのイラストがほとんど手書きで正直見づらいところもあったが、’immune memory is a nice idea but is a laboratory artefact. Only pre-infection antibodies are protective’とおっしゃっていたのは現在のワクチンに対して一石を投じているようで、興味深かった。
<6日目>
最終日は胎盤における母子感染がなぜ引き起こされにくいのかについて発表をされていたDr. Carolyn Coyneの発表が印象的だった。彼女はウイルス感染に抑制的に働くmicroRNAを同定しているのだが、実験結果も然ることながらmicroRNAの同定に至るまでストーリーが非常にわかりやすかった。Dr. Zhijian James ChenはDNAセンサーとして注目されているcGAS研究の第一人者であるが、どのようにcGASの研究が進んできたか説明をしていた。河岡研究室のJournal Clubでも取り上げられた論文の内容にも言及しおり、cGASやIFIT16などDNAセンサーはしばらく熱い研究分野になるのかなぁと感じた。この日の最後の発表は、様々なウイルスにおいて、幅広い交差防御効果を示すような抗体(たとえばインフルエンザウイルスのHA-stemに対する抗体:FI6を作成している)を研究している第一人者のDr. Antonio Lanzavechiaだった(恥ずかしながら、HA-stemに対する抗体誘導の実験を行っているにもかかわらず、この先生の仕事と名前が一致しておらず「なんでこの先生を知らないの?」と先生から注意を受けてしまった。今後は研究内容だけでなくPIにももっと注目しなくてはいけない)。様々なウイルスで交差防御効果を示す抗体の予防または治療効果のデータを示しており、どのデータも綺麗だった。また、FcRと抗体とのAffinityを弱くした方が抗体の効果が高いと説明しており、我々のプロジェクトでもその部分について検討すべきだと感じた。
<IMUS2014に参加して>
M2の時に札幌で行われたIUMS2011に参加したが、当時は正直どのような講演を聞くのがよいのか、それぞれの発表にどれくらいのインパクトがあるのかいまいち良く理解できなかった記憶がある。今回も残念ながら英語の聞き取りが不自由なせいで、分野によってはほとんど理解できない発表もあったが、多くの発表について興味深く聞くことができた。また、様々な発表において、発表者の話している事すべてをそのまま受け止めるのではなく、そのdataが何を示しているのか、そして発表者はどのように解釈していて、どのように結論付けているのかについて常に考えながら聞くことができたと思う(先生から回ってくるreviewのおかげかもしれません)。また、会場でも、みんなで話したが、女性の研究者がバリバリ研究をしていて、良い意味で男女格差がないのだなと感じた。そういった意味では、まだ日本はジェンダー後進国だと思う。
今回人生初の北米大陸で、時差ボケがひどく、あまり睡眠をとれなかったことも良い思い出となった。(時差ボケは好きではないが、)今回のような機会があったらぜひまた参加したい。
D3 浦木隆太
今週はモントリオールで行われたIUMS2014学会報告をさせていただきます。IUMSは、3年に一度、virology, bacteriology, mycology合同で開催される国際学会である。午前中のpreliminary sessionでは、様々な微生物を代表する研究者たちが、最近のトピックスやメッセージを述べ、午後のworkshop sessionでは、個々の分野での発表が行われ、influenza sessionで私も発表の機会をいただいた。今回初めて国際学会に参加したが、特にpreliminary sessionの演者たちが、国籍性別問わず、話す英語の訛り関係なく、自分の分野の研究について熱く語る姿に感動しました。女性の研究者が多く、ラボの研究を主導している様子に勇気をもらった。みんなかっこよかった!また、ウイルスだけでなく細菌・真菌/酵母などの分野と合同であったため、気になる演題があれば分野を問わず聴講できたのも魅力的であった。日本であまり問題にならなくとも、endemic地域ではcommon diseaseとして重要な感染症研究のお話を聞けたことも貴重な経験であった。特に興味のある、微生物遺伝子の進化・感染する宿主とのco-evolution・感染症の宿主特異性についての講演について、心に残った演題を挙げる。
7月28日(月)
Bridging session <ハンセン氏病のgenome-wide comparison>
中世を機に一度消滅したはずのハンセン氏病が再燃し、世界各地でendemicを起こしている問題について。2008-2012年に世界中で、23000人もの患者が発生している。この発表の面白い点は、phylogeny, geographic, chrono(Time)の視点から、ハンセン氏病の再燃の原因を解明し、対策を展開している点である。演者の研究グループは、世界各地の患者のskin biopsy・中世の患者骸骨からライ菌DNAを抽出し、array-based capture of M.leprae DNA⇒次世代シークエンスにより配列を決定した。中世と現代、地理的分布の観点からM.leprae DNAを比較することで、中東でdominantなSNP type2Fは中世時代のヨーロッパに由来すること、現在のアメリカで流行しているSNP type3Iはヨーロッパに起源を持つことが分かった。私はここからの解析の仕組みを正確に理解できなかったのだが、演者らはSNPによるminimum spanning tree(最小全域木)を作製することで、中世時代にヒトで流行っていた株がアルマジロに感染し保存され、また近年ヒトへ感染する、back-to humanの形をとり、再燃していることが推測している。
私は、ハンセン氏病患者を本でしか見たことがなく、過去の知識でしかないと思っていたのだが、このように時を巡りre-emergeすることが人畜共通感染症の怖さである。この発表のような、時代超えて行うGenome-wide comparisonは、骨格が崩壊するハンセン氏病だからこそ可能だったと思う。しかし、その他の感染症でもできれば、微生物の遺伝子進化を深く理解でき、未来の流行への対策を講じるヒントとなるダイナミックな仕事だと思います。
7月29日(火)
1.Preliminary session <chikungunya virusのE2E3はワクチン候補になりえる>
演者はシンガポールの女性であった。黒髪ボブのセンターパーツの美女で、かっこよかった。
またしてもchikungunya感染症は見たことがありません。アフリカ帰りの方の発熱・関節痛で一瞬頭に浮かべるような病気のイメージです。日本では馴染みがないが、2005年からre-emergeしており、問題となっている。発表では、現在までの知見に加え、Chikungunya virusに感染させたサルから経時的に血清を採取し、産生された抗体のB cellでの認識部位をmappingすることで、chikungunya virusのstructure protein E2E3がワクチン候補となるのではという報告である。細かい部分は理解できない箇所もあったのだが、面白かったのは、chikungunya virusが骨芽細胞に感染することにより、RANKL/OPGシステムのバランスを崩し、破骨細胞が活性化するように傾く。IL-6, RANKL↑によりリウマチ様の関節痛が起こるということであった。
聞いたことはあっても実際に見たことのない感染症は、はっきり言って実感がわきません。リウマチでも同様にRANKL/OPGシステムは崩されると言われていますが、chikungunyaは症状が数か月にわたることもあると言われているのに対し、リウマチは一生付き合う慢性疾患である違いはどこから来るのでしょうか。
7月30日(水)
Bridging session <S.typhiの宿主特異性>
Salmonella typhiは、Salmonella属で唯一ヒトのみに感染し腸チフスを引き起こす。Salmonella属に、マウスに病原性を示すS. Typhimuriumがある。S.typhiもS.Typhimuriumも共にマクロファージに感染するが、S.typhiはマウスのマクロファージには感染できない。何故か。今までにウイルスにおける宿主特異性(例:インフルエンザウイルス)は知られていたが、細菌において宿主域を超える遺伝子進化はほとんど知られていなかったらしく、大きな発見ということだ。
演者らは、病原であるtyphoid toxinの小胞輸送メカニズムに注目し、S.typhiは細菌を輸送する小胞にRab32などが直接働くのに対し、S.Typhimuriumに感染したマウスでは、effectorタンパクGtgEを分泌しRabを分解することでRab32を誘導しない、すなわちGtgEが宿主域を分けていることを明らかにした。SiRNAでRab32を抑制したマウス細胞でS.typhiが増殖することも確認している。面白いことに、Rab32の遺伝子変異は、結核・leprosyの感受性、及びChediak-Higashi症候群のような遺伝病にも関わっていることが次々報告されているとのことで、今後の研究が期待される。
ウイルスと細菌は全く異なるが、どちらも進化の過程で、宿主に適応するメカニズムを得てsymbiosisを保っている点では同じである。ウイルスはヒトのメカニズムを乗っ取らないと繁殖できないからこそ、インフルエンザウイルスでもまだまだ宿主域に関わるメカニズムが隠れているのではと思います。
7月31日(木)
1.Preliminary session <BIOFIFM!!>
細菌に晒されることでウイルスは感染性を上げる、という話です。これを思い付いたきっかけは話されていたのでしょうか、気になります。全く概念として知らないことなのに、とてもわかりやすく、聞き手に分かりやすく説明するにはどうすればいいか、スライド・プレゼン方法なども勉強になりました。
演者らは、感染性を挙げる要素の一つとしてウイルスの安定性に注目し、安定性をもたらす細菌要素を探索した。腸管normal floraが持つLPSの要素であるGlcNAcが長ければウイルスが安定することから、LPSが付着するcapsid proteinに変異を入れ、ウイルスの安定性が低下することを示した。LPSによりウイルスが集合することで安定性が上昇することを、電顕・Dynamic light scattering(仕組みはわからない)・遺伝子解析により証明している。
ウイルスの生存が細菌に助けられるなら、その逆も沢山ありそうです。今回関わっているのが正常細菌叢なのは気になりますが。インフルエンザ感染後、PAFレセプター増殖により肺炎球菌に感染しやすくなる仕組みとは異なるかもしれませんが、色んなところで微生物が共存している様子は面白いと思います。
2.Preliminary session <ハエ体内でのanti-viral機構: RNAi>
機構を持つことで、微生物を次の宿主へ受け渡すことができる。RNAiによる抗ウイルス応答は、ウイルス遺伝子由来のSiRNA作成、RNAi mutantのウイルス増殖、silencing signalの全身への広がりなどにより行われる。演者らはago, DCR2遺伝子をKOしウイルス感染が抑制できないことを示し、抗ウイルス応答にRNAiがハエ全身に広がることが必要であることも示している。また、dsRNAの取り込みに必要な遺伝子をKOしたハエではウイルス増殖を制御できず、その効果はRNAi依存的であった。すなわち、ハエにおけるRNAiによる抗ウイルス応答はハエ全身、細胞、そして宿主間を通して重要であるらしい。
昆虫が宿主とウイルスを媒介する場合、感染制御は難しいと言われますが、ハエが上記のような抗ウイルス応答の仕組みを持っていると、ウイルスが変異を起こしたところでハエの生存への影響はあまりなく、感染制御はあくまでヒトで行うしかないと考えられます。蚊、ハエ、ダニ媒介の感染症は数多くありますが、どのように制御すればいいのでしょうか。
D4 山地 玲奈